
活字組版印刷の体験
2018年8月17日、ウェスタ川越にて、學のまちkawagoe実行委員会主催のイベント「文字のこと、本のこと。」が開催された。小学生から年配の方まで、幅広い年齢層の多くの市民の方が参加され、大盛況であった。
『活版印刷三日月堂』から——活字組版印刷の体験
このイベントのきっかけとなったのは、『活版印刷三日月堂』全4巻(ほしおさなえ著、ポプラ社、2016-2018)であろう。この小説は、川越の小さな活版印刷所を舞台にしている。
三日月堂店主の月野弓子が、桐一葉という珈琲店を経営する岡野からの依頼でショップカードを印刷し、さらにコースターを印刷してみる場面がある。
「そうだ、これは依頼とは別なのですが、ちょっと組んでみたものがあって……。いま、版が機械にセットされていますから、刷るところを見てみませんか?」
「え? ええ……」
僕が頷くと、弓子さんが少し含み笑いをした。以前手キンと教えてもらった丸い機械の側に立つ。ぷんとインキの匂いがした。
「これが版です」
弓子さんは機械の下の方の垂直になった部分を指した。たしかに活字が並んでセットされていた。でも、一行だけだ。
「これって……もしかして俳句?」
目を凝らした。文字が小さいうえに左右反転しているので、ほんの数文字しかないのになにが書かれているのか、すぐに読めなかった。
「じゃあ、刷りますね」
弓子さんが機械のうえについている円盤にインキを少し出した。レバーを動かすとインキがくるっとのびて広がった。
活字の向かい側の壁に小さな正方形の紙をセットし、大きなレバーをさげる。ハンコが押されるように、活字が紙にくっつき、離れると文字が印刷されていた。桐一葉日当りながら落ちにけり
息を飲んだ。
「これは……」
「コースターです。俳句のお話が面白かったので、遊びで作ってみました」
弓子さんが機械から四角い紙をはずし差し出した。ふんわりとした手触りの紙の右端に、縦書きで桐一葉の句が印刷されている。印刷されているのはそれだけ。あとは真っ白。句の活字から声が響いてきそうで、心が震えた。
この場面を追体験するような、金属活字組版による印刷体験のワークショップ。担当は中野活版印刷店の中野好雄さんで、立教大学の学生さんが手伝っていた。小学生から年配の方まで、幅広い年齢層の多くの市民の方が参加され、大盛況だった。
最初に自分の名前を書いて、活字棚から活字を拾う。漢字はなく、ひらがなだけだ。あらかじめ組み付けられているところに、拾った活字を名前の通りに並べてセットすることで活字組版ができあがる。
それを手キンと呼ばれている活版印刷機にセットして、中野活版印刷店特製の丸いコースターに印刷する。ハトメパンチでハトメを打ってコースターの完成だ。このコースターがお土産となる。
最後に組版をばらして使った活字を元の位置に戻す。ここまでやって体験の終了ということなのである。
『男はつらいよ 寅次郎恋愛塾』から——写真植字機の実演・解説
渥美清主演の『男はつらいよ 寅次郎恋愛塾』(山田洋次監督、松竹、1985)は、樋口可南子の演じる江上若菜が写植オペレーターという設定である。HDリマスター版DVDの廉価版が2017年に発売された。
この映画に写植の話題が出てくる場面がある。まず、東京の彼女のアパート「コーポ富士見」での寅次郎と若菜との会話。寅次郎が机の上に置かれた小型の写植機に目をとめ、カバーをめくる。以下、DVDからの書き起こしである。
寅次郎 「ねぇ、これなんだい、これ」
若菜 「あっ、それ? 写植の機械」
寅次郎 「写植?」
若菜 「そう」
寅次郎 「ほう、なんの仕事してんの?」
若菜 「印刷会社に勤めてるの。それは内職」
寅次郎 「あっ、そう。俺の妹の亭主も印刷工だよ。もっとも、すぐ潰れちまうようなちっぽけな工場だけどね」
若菜 「あら、そう」
寅次郎 「なに、会社休み?」
若菜 「それがね。おばあちゃんの後始末でゴタゴタしてて、一週間ほどよけいに休んじゃったの。有給休暇があるからかまわないと思っていたんだけど、他の人は誰も使ってませんなんて、上役がグチグチ言うもんだから、頭にきて辞めちゃったの。いいの、どうせ睨まれてるんだから」
寅次郎 「で、これからどうするんだい」
若菜 「当分は失業保険があるし、あとは内職を探してやっていくわ。なんとでもなるわよ、食べるぐらい」
寅次郎 「まあ、そう言わねえでさ。ちゃんとした勤め口、探せよ。及ばずながら、俺も力になるから」
若菜 「ありがとう」
寅次郎 「すっかり長居しちゃったな。じゃ、また来るわ」
団子店「くるまや」に戻った寅次郎は、「朝日印刷」のたこ社長、博、さくらたちに、若菜のことを話す。この後しばらくして、博の紹介で入った新しい職場で、大型の写植機を操作している若菜の姿があった。その職場では数台の写植機が稼働しているようだった。
この映画が公開されたのは1985年である。手動写植機がもっとも華やかだった頃だ。若菜が内職用として、自室で所有していたものと同じような卓上写植機が、それから30年以上経った今、実際に動いているところを見ることができるのだ。
ワークショップでは、写植機SPICA-AHを動かしての実演と解説があった。担当しているのは株式会社文字道の伊藤義博さんである。多彩な文字盤や、説明パネルなどの展示コーナーも充実していた。
自分の名前の漢字を文字盤から探して、レバーを操作して印字するという体験は、こどもたちに大人気であった。実際に印画紙に焼き付けるということまではできなかったが、写真植字とは何かということは理解できたと思う。
今も稼働している手動写真植字機は多くはない。それだけに、20世紀の印刷文化に大きな役割を担った写真植字機を体験する貴重な機会になった。
『本のエンドロール』から——デジタル・タイプセッティングの実際
『本のエンドロール』(安藤祐介著、講談社、2018年)という小説には、DTPオペレーターとして豊澄印刷データ制作部の福原笑美が登場する。
福原の仕事はDTPオペレーター。データ上で印刷の版を組む仕事だ。
インデザインというDTPソフトを駆使して、組版データを作ってゆく。
ページの余白部分に記載する章タイトルは〝柱〟と呼ばれる。柱の位置も、編集者によって指定されている。
淵田の本は、指定に従い奇数ページ下の小口寄りに横書きで柱を入れる。ノンブルと呼ばれるページ番号も振る。ノンブルはフランス語であり、英語の「ナンバー」にあたる。
これらの作業はインデザインによって自動化されている部分が多いが、この後、奥平が赤字で入れた指定に従って、難読漢字の右側にルビを振る。
作業開始から一時間半、時刻は十九時四十五分。全てのルビを振り終えた。
この小説で描かれたような、現在のデジタル・タイプセッティングがどのように行われているかについても子供たちに知ってほしかったので、InDesignでの組版を画面表示したPCを展示した。説明は櫻井印刷所のアートディレクター中榮康雄さん。
現在のPCによるデジタル・タイプセッティングは、金属活字組版、写真植字を引き継いでいる。活版印刷機、写真植字機と並べて、同じワークショップで見ることができたということも意義のあることだと思う。

川越ワークショップ

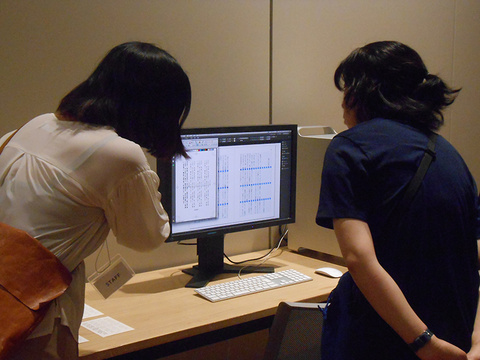
写真植字機の実演・解説
デジタル・タイプセッティングの実際